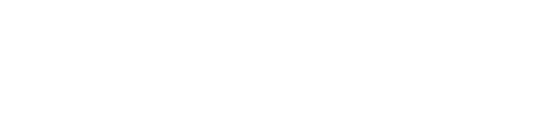竹バチの製作

秋を感じさせない暑さが続いておりますが、今年も秋祭りの季節がやってきました。当組も本日から準備を始めています。準備物のひとつが道具です。今回は半太鼓のバチを作りました。
半太鼓のバチ製作
当組が使う獅子舞道具の中でも半太鼓のバチ(桴)は特に消耗が激しく、毎年6〜8本が折れ・割れ・欠けにより使えなくなります。破損したバチは太鼓を痛めるため、バチの状態維持は大切です。
ここ数年は主に樫の木で作ったバチを使ってきましたが、樫材の高騰や加工コストの観点から、難しくなってきました。とはいえ、既製品のバチを購入すると1組で数千円はかかります。そこで今年は竹バチを自作することにしました。
樫のバチと比べると音は軽いものの、しなりによってキレのある音が出せるのが竹バチの良さです。
用意したもの

材料
- 使わなくなった竹刀
- 熱収縮チューブ(φ12mm)
- グリップテープ
- エンドテープ(ビニールテープ)
道具
- コンベックス
- 鉛筆
- 竹ひきのこ
- 作業手袋
- ベルトサンダー
(ヤスリ60・180番) - ハサミ
- ドライヤー
何に使うのかわからないものもあると思いますが、
少しずつ説明していきます。
竹刀からバチを作る理由
製作時間の短縮
伐採した竹はすぐ使えず、油抜き(表面の油分を取り除く作業)をした後、数年をかけて乾燥させる必要があります。竹刀にはその工程を済ませた竹が使われているため、製作の手間を大きく省くことができます。
高品質な材料
竹刀には厳選された良質な竹が使われています。特に最近の竹刀は剣道連盟の安全基準を満たすよう作られており、形状・強度などの品質が保証されています。真っ直ぐで耐久性の高い竹はバチにうってつけです。
製作の容易さ
竹刀は4本の竹片を組み合わせて作られています。そのため、分解するだけで4本(2組)のバチができます。竹片の重さや重心も整えられており、竹の表面も研磨済み。簡単にバチが作れます。
中古竹刀の手配

竹刀は体育の授業で使った後、持て余している人も多いのではないでしょうか? 数本程度なら竹刀は集まります。しかしバチの消耗度合いを考慮すると、もう少し欲しいところ。今回は幸運にも大量の竹刀をお安く譲ってもらうことができました。
竹刀には真竹・桂竹・カーボンなど種類があります。譲っていただいたのは桂竹の竹刀。真竹と比べると質は劣りますが、充分高品質です。状態の良い竹刀はもったいないので除き、バチを作っていきます。
竹バチの作り方
参考までに竹刀からバチを作る方法をご紹介します。
1. 竹刀の選別
竹刀は材質だけでなく、長さ・重さ・重心の位置・柄の形状によっても分類されています。
長さは2尺8寸〜3尺9寸(約85〜118cm)と幅があります。短い竹刀はそのままバチとして使えそうな長さですが、柄の部分は竹片にすると角ばっているため、研削して持ちやすく整える必要があります。柄の形状によっては加工が難しいこともあります。一方、長い竹刀は柄の部分を切り落とすだけでバチとして使えます。そのため、長い竹刀の方が竹バチ製作には向いているかもしれません。重さも長さに比例するので、重めのバチを作る場合にも長い竹刀が有利です。
重心にも注意が必要です。一般的な竹刀は重心が中央にあるため、柄を切り落とすことで自然と重心が手元に寄り、扱いやすいバチになります。逆に重心が手元から離れたバチは破損しやすいと考えられます。竹刀には同張型(手元重心)や古刀型(先端重心)といった種類があるため、製作の際は重心の位置を確認することをおすすめします。

上の写真は上から39(大学生・一般用)、38(高校生用)、37(中学生用)、36(小学生高学年用)でそれぞれ長さ・重さが違います。すべて重心は中央で、柄は丸型。最も一般的な竹刀です。今回はこの中から39と37を使って4組(8本)のバチ(試作品)を作ります。
2. 竹刀の分解


竹刀をバラしていきます。まずは中結と弦をほどきます。
ほどくと弦がゆるみ、それぞれの部品を取り外せるようになります。



先端の先革と先ゴムを取り外し、柄革を引き抜くと、竹刀をバラせるようになります。
竹片は契という金具によって固定されているため、先端から裂くようにして取り外します。

竹刀を分解するとこんな感じです。竹片の幅や節の位置は揃っていますが、稀に幅の異なる竹片で組まれていることがあります。その時は同じ幅の竹片を選んでペアにします。
3. 切断の位置決め
竹片を切る位置を決めます。最も無難なのは先端からバチに必要な長さ分だけ切り取る方法。長めの竹刀であれば、最も幅が広くなっている第三節あたりが手頃です。今回は以下の位置で切ることにしました。

①は2尺8寸(約85cm)、②は2尺5寸(約76cm)、③と④は2尺2寸(約67cm)になる想定です。
④は節を先端にして縦割れしにくくする狙いがあります。
切断する位置に鉛筆で印をつけて切っていきます。
4. 切断

竹片を固定して、竹ひきのこで切ります。
普通のノコギリでも切れますが、刃の目が荒いと竹を痛めることになるので、目の細かいノコギリがおすすめです。

このように切れました。ほぼ完成です。
ここからはバチとしての品質を高めていきます。
5. 研削・研磨


竹片の節はそのままでは太鼓を痛めかねないので、荒目のヤスリで削ります。ベルトサンダーなどの電動工具を使えば一瞬ですが、ない場合は紙ヤスリをレンガなどに固定して削るという方法もあります。竹片の表面は既に処理されているので、削るのは裏面のみです。
電動工具を使う時はしっかりと固定し、作業手袋をします。軍手は糸を巻き込んだり、すべりやすいため、おすすめしません。


竹片の先端も角がなくなるよう、丸く削ります。


仕上げはヤスリの目を細かくして、滑らかになるよう研磨します。

研削・研磨が終わりました。手元部分は後で加工するため、そのままにしています。
6. 先端の強化


竹バチの破損で最も多いのが縦割れです。そのため①と②のバチには補強を施すことにしました。
使用するのは熱収縮チューブ。電線の保護などに使われる部品です。適当な長さにハサミで切って、ドライヤーで熱を当てるとチューブが収縮して固定されます。糸やテープを巻く方法もあります。
7. 持ち手の加工

バチを持ちやすいようグリップテープを巻きます。グリップテープはスポーツ用品店で購入できますが、大量に使う場合はロールでまとめ買いした方がお得です。メルカリなどで格安で販売されています。
ウェットやドライなど種類があり、巻き方もいろいろありますが、好みで良いと思います。

巻き終わりはビニールテープで固定します。本来はエンドテープという仕上げ専用のテープで巻きますが、高価なためビニールテープで代用しました。色も豊富に選べるのでおすすめです。

グリップテープは右のバチは右手で、左のバチは左で巻くと良いです。握った時に指とテープの向きが揃うので、めくれにくくなります。

あえてグリップテープを巻かない選択肢もあります。滑り止めのある手袋をしてバチを打つのなら不要ですし、竹刀の銘がある場合は、それを活かせます。
8. 完成
完成したバチがこちらです。


今回はテープの色を黒で統一しましたが、仕様の異なるバチを同時に使う場合、バチのペアが見分けづらくなります。グリップテープやエンドテープの色をそれぞれ変えるなどの工夫が必要かもしれません。
バチの仕様をすべて統一する方法もあります。片方が破損しても替えが効きやすいからです。今回は試作のためすべて異なる仕様でバチを作りましたが、実際は仕様を統一することになると思います。
香川県の獅子舞は道具だけを見ても、獅子組ごとに仕様が異なります。今回ご紹介したのは、数多くある作り方のひとつとして参考にしていただければと思います。
祭り道具を自作する意味
かつて祭りの道具は、自らの手で作るのが当たり前でした。しかし近年では商業化が進み、材料や技術に触れる機会が少なくなったことで、既製品や外注に頼ることが増えています。お金をかけてでも祭りを続ける姿勢は尊いものですが、祭り道具を自作することには「費用削減」を超えた価値があると感じます。
まず、自ら手をかけて作り上げた道具には、唯一無二の個性が宿ります。見た目が悪くなることもあるかもしれません。しかしそれが作り手の痕跡として愛着を深め、祭りにかけがえのない温もりを添えます。そして、その道具を手にしたとき「自分たちの力で祭りを支えている」という誇りが胸に刻まれます。道具を生み出す過程そのものが「祀る」という行為につながっているのです。
祭り道具は単なる備品ではなく、その土地の人々の想いを映す鏡です。すべて自作することは難しくても、できる限り自らの手で生み出し続けることが、「祭りを受け継ぐ心」を未来へとつなぐ道なのではないでしょうか。